こんにちは、いつもアグクルの記事を読んでくださりありがとうございます。
発酵を次世代に伝えるアグクル代表の小泉泰英です。
今回は甘酒の栄養についてお伝えしていきます。
甘酒とは、日本の伝統的な甘味飲料の一種で、酒粕から作られるもの、米麹から作られるものの2種類があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
 甘酒には2種類ある!米麹甘酒と酒粕甘酒の違いとは?
甘酒には2種類ある!米麹甘酒と酒粕甘酒の違いとは?
「1分でわかる!」と書きましたので、1分以内で知っていただけるようにまず結論からお伝えします。#F5B1F1
さらに詳しく読みたい方は1分以上かかりますが、栄養だけでなく、腸内との関係や注意点なども解説していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
 【苦手だったのに、毎日飲んでしまう】糀100%の甘酒「こうじつ」
【苦手だったのに、毎日飲んでしまう】糀100%の甘酒「こうじつ」
目次
甘酒ってどのくらい栄養があるの?

- 甘酒の20%がエネルギーになるブドウ糖
- ビタミンB類が甘酒のブドウ糖をエネルギーに変える
- 甘酒には体内合成ができない必須アミノ酸の全種類を含有
①甘酒の20%がエネルギーになるブドウ糖
甘酒の主成分はブドウ糖で、全体の約20%含まれています。
ブドウ糖は脳の唯一の栄養源で、私たちの活動のエネルギー源にもなる大切な栄養です。
ブドウ糖は血液中では血糖として存在しており、インスリンによって濃度がコントロールされています。
インスリンとは糖の代謝を調節し、血糖値を一定に保つ働きを持つホルモンです。
血液中のブドウ糖濃度が上がると、インスリンの働きでブドウ糖が中性脂肪に変えられ、脂肪細胞として蓄えられます。
ただし、この脂肪細胞が溜まり過ぎてしまうと、太る原因になるので注意が必要です。
②ビタミンB類が甘酒のブドウ糖をエネルギーに変える
甘酒には、ブドウ糖をエネルギーに変える働きを助けるビタミンB類が多く含まれています。
甘酒には多量ではないものの、ビタミンB1、B2、B6やナイアシン、葉酸といわれるビタミンB類が含まれています。
ビタミンB類は酵素と結びつくことで、ブドウ糖をエネルギーに変えることができるようになります。
つまり、甘酒にはエネルギーになるブドウ糖とエネルギー変換を助けるビタミンB類の両方が含まれているので、効率よく私たちの活力になるエネルギーを生み出すことができるのです。
③甘酒には体内合成ができない必須アミノ酸の全種類を含有
甘酒の栄養としてもう一つ挙げられるのが必須アミノ酸の全種類をしていることです。
たんぱく質を構成するアミノ酸は20種ありますが、そのうち9種類は体内で合成できないので,食べ物からとる必要があり、これを必須アミノ酸といいます。
必須アミノ酸はたんぱく質から生み出されます。
甘酒はお米からできているため、主成分はデンプンなので、たんぱく質や必須アミノ酸の量はあまり多くありません。
しかし必須アミノ酸の量は少ないながらも全種類含有しているのが甘酒のすごいところであり、発酵の力です。
栄養だけじゃない!すごい甘酒の効果とは?
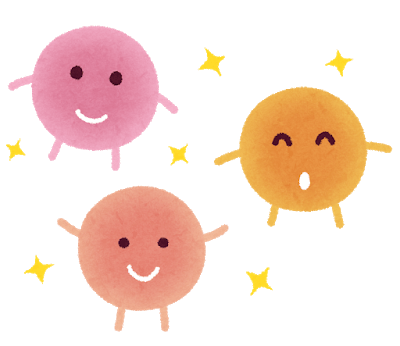
甘酒の栄養についてお伝えしてきましたが、甘酒にはまだまだすごい効果があります。
- 甘酒のオリゴ糖や食物繊維が腸内環境を整え、便秘解消や免疫力アップにつながる
- 発酵の効果で、お米が体に消化吸収しやすいように分解されているので、体にやさしい
①甘酒のオリゴ糖や食物繊維が腸内環境を整え、便秘解消や免疫力アップにつながる
甘酒にはブドウ糖以外にもオリゴ糖といわれる構造が複雑で大腸まで届く糖や食物繊維が含まれています。
これらのオリゴ糖や食物繊維は腸内細菌の善玉菌のエサになることで、腸内の活動を正常化します。
その結果、便秘の解消や予防、免疫力のアップにつながります。
②発酵の効果で、お米が体に消化吸収しやすいように分解されているので、身体にやさしい
甘酒の良さとして軽視しがちですが、すごい効果なのが、消化吸収の良さです。
食べ物は基本的に一度、消化酵素によって分解してから体内に吸収されますが、甘酒の場合は発酵の力ですでに分解されているので、身体にやさしいのです。
甘酒を作る過程で、麹菌の発酵によって、デンプンを糖に変えるアミラーゼという酵素やたんぱく質をアミノ酸に変えるプロテアーゼという酵素を生み出します。
なので厳密に言えば、菌の力で分解されているのではなく、菌が生み出した酵素の力によって分解されているんです。
甘酒を飲む上で知っておきたい2つのこと

最後に甘酒を飲む上で知っておきたいことをお伝えします。
- 甘酒は栄養バランスは豊富だけど、完璧ではない
- 生きた菌や生きた酵素である必要はない
①甘酒は栄養バランスは豊富だけど、完璧ではない
最近、いろいろなサイトで甘酒の効果や効能が記事にされていますが、多くのサイトで少し過大評価されている気がします。#A7D4E7
本記事でも甘酒の栄養についてはお伝えしてきましたが、甘酒の栄養は量よりも種類の多様性に意味があります。
ブドウ糖も摂りすぎてしまうと太る原因にもなるので注意が必要ですし、必須アミノ酸も大豆食品やお魚、お肉の方が豊富に含まれているので、甘酒だけを飲んでいれば栄養が豊富に摂れるというわけではありません。
甘酒は「飲む点滴」と呼ばれているように、水分補給やエネルギーチャージには最適ですが、あくまで補助的な役割として考えることが良いです。
とはいえ、甘酒を毎日適量(100~200g程度)飲むことはあなたの身体を元気にしてくれるので、牛乳や豆乳などと一緒に甘酒を生活の中に取り入れることが大切です。
 1分でわかる!甘酒が「飲む点滴」といわれる理由とは?
1分でわかる!甘酒が「飲む点滴」といわれる理由とは?
②生きた菌や生きた酵素である必要はない
もう一つ、甘酒についての記事の誤解があります。
甘酒は菌や酵素が生きていた方が効果があるという情報です。
しかしながら菌や酵素が生きていた方が効果があるという可能性は極めて低いです。
麹菌の役割は、お米を発酵させることで100種類以上の酵素を生み出すことです。
そしてその生み出された酵素が、あらゆる物質を分解することで、栄養素のが生まれます。
この菌と酵素によって生み出された栄養分こそが、身体にいいのであって、菌や酵素そのものではないということが重要なポイントです。
酵素が生きていることの良さとしては、酵素が生きている限り、さらに物質を分解するので栄養分が増えることです。
ですが甘酒の場合、酵素が生きた状態だからと言って、甘くなったり、ビタミンが増えたりする可能性は低いので、あまり気にすることはないでしょう。
麹菌は酵素という素晴らしい物質を生み出し、酵素は私たちの消化吸収を助けながらも栄養補給に役立つ甘酒を作ってくれるということが自然の力であり、発酵の素晴らしさではないでしょうか。#CBF5B1
甘酒の酵素についてさらに詳しく説明した記事もありますので、ぜひそちらもご覧ください。
 【結論】発酵後の甘酒は酵素が死滅しても効果は変わりません
【結論】発酵後の甘酒は酵素が死滅しても効果は変わりません
おわりに
いかがだったでしょうか?
今回は甘酒の栄養についてお伝えしました。
- 甘酒の20%がエネルギーになるブドウ糖
- ビタミンB類が甘酒のブドウ糖をエネルギーに変える
- 甘酒には体内合成ができない必須アミノ酸の全種類を含有
以上の3つからも甘酒は毎日の生活に取り入れたい飲み物ではありますが、完璧な飲み物というわけではないので、朝の一杯や疲れたときの一杯として補助的な栄養補給、エネルギー補給に最適です。
また菌や酵素は発酵過程においては重要な役割をしていますが、発酵後は生み出された栄養素に効果があるので、あまり気にせずあなたの好きな味の甘酒を摂取するようにしましょう。
ぜひ毎日の食生活の中に甘酒を加えて、発酵ライフを楽しんでみてください。
 発酵のやすくん
発酵のやすくん
 【苦手だったのに、毎日飲んでしまう】糀100%の甘酒「こうじつ」
【苦手だったのに、毎日飲んでしまう】糀100%の甘酒「こうじつ」
![AGCL[アグクル]](https://agcl528.com/wp-content/uploads/2018/12/010904b4184cefeca78b6084bb3f15fd.png)

